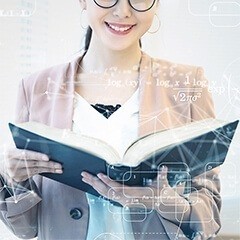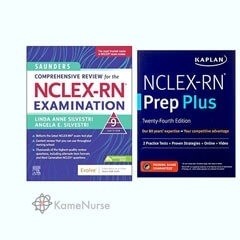浣腸と坐薬の違いをナースがとことん解説【Youtube動画付き】
こんにちは!
日米看護師のカメナースです。
この記事では、とことん浣腸と坐薬の違い、
便秘の解消法を知っていただけます。
この記事の内容
ナースがとことん解説!坐薬と浣腸の違い
レシカルボン坐薬とイチジク浣腸の比較
| レシカルボン坐薬 | イチジク浣腸 |
|---|---|
| 腸を刺激して排便を促す | 腸を刺激して排便を促す |
| 炭酸水素ナトリウムが、腸内で炭酸ガスを発生します。ガスの効果で腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を激しくなります。動き出した腸は便を排泄させます。 イチジク浣腸に比べると穏やかに作用しますので、浣腸よりもご高齢の方に向いているかと思います。 *炭酸水素ナトリウムとは、多くの入浴剤、炭酸水、ケーキを膨らますベーキングパウダーに配合されています。 | グリセリン成分が腸のかべの水分を吸収します。同時に腸の動きを亢進させます。 水分浸透作用が起きて、やわらかくなった便が潤滑化され排泄されます。 |
| 穏やかに作用する | 即、激しく作用する |
| 出血や炎症がある痔の人は使用禁止!医師に相談してください。 |
新レシカルボン坐薬S
通常は1〜2個を出来るだけ肛門内の深く入れます。重症な便秘には1日に2〜3個を数日間続けて入れる。この方法が新レシカルボン製造販売元から推奨されている使用方法です。
レシカルボン坐剤は通常20分程度で効果がでます。
イチジク浣腸
イチジク浣腸は、病院ではグリセリン浣腸、市販薬では第2類医薬品の浣腸です。
浣腸挿入の目安:成人:5~7cm、小児:3~4cm
使用する際は、体温程度に温めて使用して下さい。高齢者・全身状態が悪い患者さんでは使用することによって急激な血圧低下をきたすことがありますので、30~60ml程度の量から注意して使用する必要があります。
浣腸を使うときの正しい姿勢と入れ方・動画
浣腸をする時の姿勢
浣腸をする時は、直腸やS状結腸の走行から考えると左側臥位(左側を下にした横向きに寝た姿勢)が最も適切な姿勢です。

浣腸の入れ方
浣腸の先端をゆっくり肛門に入れて、大人の場合5−7cm 奥に進めます。
体温程度に温めた、浣腸の液の注入は、抵抗感や痛みがないことを確認して、ゆっくりと浣腸液を入れてください。
*浣腸の液の注入の最中に、お腹に圧がかかり過ぎていますと、直腸の前側の壁と浣腸先端の角度が鋭角になり、その状態で、勢いよく液を注入しますと穿孔(腸壁が破れる)危険があります。
左側を下にした横向きの体位で、大きくゆっくり深呼吸しながらリラックスし、ゆっくり浣腸の液を注入してください。
Youtube視聴者さまからの相談内容
浣腸や坐薬に関する質問
大量使用により、急激な血圧低下をきたすことがあります。浣腸の場合は、30~60ml程度の量から注意して使用する必要があります。使用量が増えているようですので、医師にご相談ください。便秘の種類を見極めるのも大切です。
体力が落ちているとき、使用量が多すぎてしまったときは、副作用によって、気持ち悪い、冷汗、顔面蒼白、手足の冷え・しびれ、耳鳴り、息苦しい、胸苦しさ、めまい、脈が速い・弱い、血圧低下、目の前が暗くなり意識が薄れるなど、怖い症状が出てしまうこともあります。ご自身の体調と、使用量を十分に考えて使用ください。
坐薬と浣腸の併用によっても、同様の副作用が出ることがあります。医師から指示を受けた使用量、販売会社からの推薦量を必ず、お守りください。
浣腸や坐薬を使う便秘の種類
便秘には、3種類のタイプがあります。

- 直腸便秘(習慣性)
多忙、環境の変化、痛み、不規則な生活などにより、便意が繰り返し抑制されたり、下剤や浣腸の乱用などによっておこる便秘です。これは直腸内の圧に対する感受性が低下している状態で、直腸内に便がたまっても、便にいきたいと思う感覚がなくなっているます。 - 弛緩性便秘(しかんせい)
食事量・食物繊維の摂取不足、運動不足、加齢、経産婦、長く寝込む、などが原因になる便秘です。腸への機械的刺激が不足しているため、腸の動きが低下します。その結果、腸の内容物が大腸に貯まり、便から必要以上に水分が吸収され、少量の硬い便が形成されます。 - 痙攣性便秘(けいれん)
精神的ストレスや過敏性大腸炎症候群に代表される便秘で自律神経失調により、大腸の下の部分が過度に痙攣性の収縮をするために、腸の内側の膜が狭くなり、大腸内の容物の輸送に時間がかかる状態です。便は硬く少量で、時に兎糞状(とふんしょう)うさぎの便の様な、小さい硬いコロコロした便の形になります。
『習慣性べんぴ』は、文字通り、習慣が良くなかった過去の産物として、苦しい状態があるということです。
ナースもサラリーマンも忙しい生活に追われてます。『習慣性べんぴ』は、糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症など、生活習慣病の仲間ともいえると私は思っています。
この『習慣性べんぴ』は、生活習慣病と同じく、早い対応、習慣の改善で良くなります。
便秘|各医学会の定義
日本内科学会|便秘定義
多くの医療従事者が認識している「3日以上便が出てない状態」。学会では、これに「毎日排便があっても残便感がある状態」を加えています。
日本消化器病学会の定義
「排便が数日に1回程度に減少し、排便間隔不規則で便の水分含有量が低下している状態(硬便)を指す」としています。オピオイドの有害事象である便秘は重篤なものもあるため、日本緩和医療学会では、便秘を定義し「腸管内容物の通過が遅延・停滞し、排便に困難を伴う状態」とされています。
『慢性便秘症診療ガイドライン2017』(南江堂)の定義
「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」とシンプルに定義されています。
便秘になる理由
女性ホルモンの影響
女性ホルモンは体内に水分を蓄積しようとする働きがあります。
ホルモンバランスのくずれは、排便に十分な水分が補給されなくなります。そのため、便秘になりやすくなります。
腹筋の力の低下
女性は男性に較べて排便に必要な括約筋、腹筋の力が弱いため、便秘になりやすい傾向があります。
排便を我慢する
外や人前で便意を催した時に、気恥ずかしさもあって排便を躊躇したり我慢したりすると便秘になる傾向が強くなります。
ダイエット
ダイエットすると腸が不安定になり腸動き(蠕動運動)が弱くなります。
便秘薬の乱用
便秘薬の乱用により使用しないと排便できなくなる傾向になります。

便秘を改善して坐薬と浣腸を使う回数を減すには
◆ 毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけて、排便しようとこころみる。できれば寝起き後、最初の食後がベストタイミング。
(長く便器に座り過ぎ注意してください。痔になりやすくなります。)
◆ 便器に座っている間に、 腸を動かすツボ刺激と、 お腹マッサージを交互にする。
◆ 食後3時間後にお腹のマッサージを行う。
◆ 寝る前にもお腹のマッサージを行う。
◆ 運動をして、腹筋を鍛える。
◆ 起床時に水や牛乳、ココア、お茶などの、水分を飲む。
◆ 日中も十分な水分を摂取する。
◆ 食事の前に水分を摂取する。
◆ 1日3食、消化吸収のよい炭水化物を食べる。
◆ 発酵食品を食べるように心がける。
◆ オリーブオイルなどの良質の油を摂取する。
◆ 痩せる為のダイエット中の人は、不溶性食物繊維を 摂取するように心がける。
◆ 暴飲暴食をしないように心がける。
辛い便秘、坐薬と浣腸を使う頻度を減すために、食生活の改善、規則正しい排便習慣をつけること、明日からから始めてみてはいかかでしょうか。
著者・動画制作:日本看護師、アメリカ・ニューヨーク州、カリフォルニア州国際看護師、1級ネイリスト カメナース